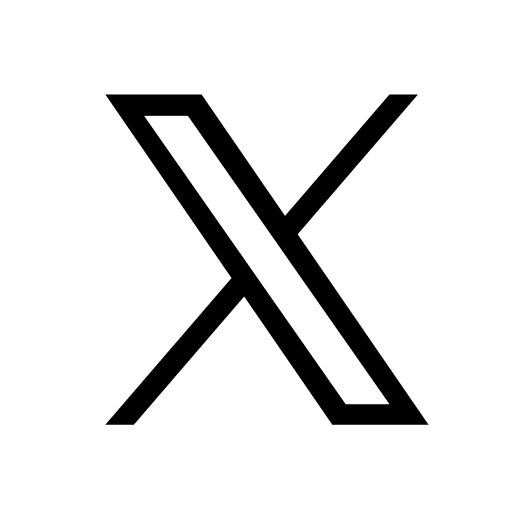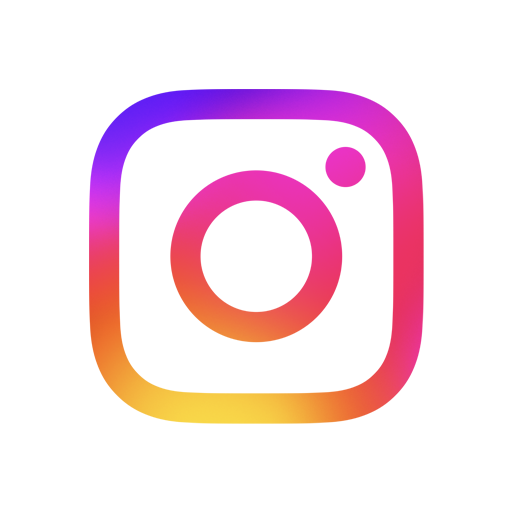今月のおススメ本-ルポ 教育困難校-
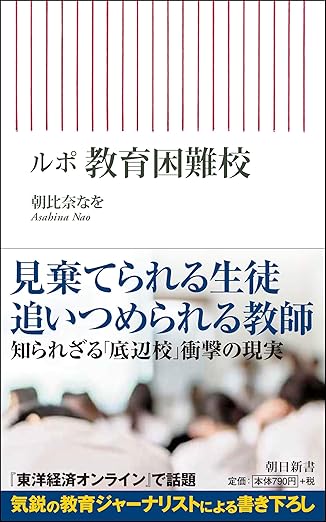
著者:朝比奈なを
出版社: 朝日新聞出版
詳細URL:https://amzn.asia/d/9vlkr9t
「教育困難校」のリアルとは? 先生と生徒が向き合う現場を描く一冊
「教育困難校」とは、学力の遅れや生活指導の課題を抱える生徒が多く、授業の成立が難しい高校のことを指します。本書では、そうした学校の現場で奮闘する教師や生徒たちの姿がリアルに描かれています。
私自身、中学時代は荒れた環境の学校に通っていたため、本書の内容には共感する部分が多くありました。授業を聞かず友達と話す生徒、先生にタメ口を使う生徒、派手な外見の生徒——そうした同級生たちに囲まれながらも、彼らは根が優しく、仲間に対しては情が厚い人が多かったと感じています。一方で、指導に苦労する先生方の姿も目の当たりにしていました。本書を読むと、そうした現場で生徒の将来を支えようと奮闘する先生たちの努力が改めて伝わってきます。
本書のレビューを見ても、「教育困難校の実態を知らなかった」「勉強ができない=努力不足ではないと気づかされた」といった声が多く見られます。ある読者は、「彼らは社会の被害者ではないか?」と問いかけています。実際、家庭環境や経済的な事情によって学ぶ機会を十分に得られなかった生徒は少なくありません。しかし、彼らの多くは人とのつながりを大切にし、仲間を助ける気持ちを持っていることが本書を通じて伝わってきます。
教育困難校の教師たちは、学力の向上だけでなく、生徒が社会で自立できるよう日々サポートを行っています。その現場の苦労や葛藤は、もっと評価されるべきではないでしょうか。本書は、単なる学校の問題にとどまらず、日本の教育制度全体を考えるきっかけを与えてくれる一冊です。興味のある方は、ぜひ手に取ってみてください。
今月の言葉
人生に失敗がないと人生を失敗する
斎藤茂太(精神科医)
斎藤茂太さんは、詩人・斎藤茂吉の息子であり、精神科医としても活躍しました。
大切な試験やテストの日、誰もが「失敗したくない」と思うものです。
しかし、一見すると順調に見える人生でも、失敗の経験がなければ、そこから学ぶ機会も生まれません。むしろ、失敗を経験し、それを乗り越えることで、人は成長していくのではないでしょうか。
この言葉は、失敗を恐れるのではなく、それを糧に前へ進む大切さを教えてくれます。
編集後記
今月の保護者通信をお読みいただき、ありがとうございます。
つい先日、映画『アルマゲドン』を観ました。
地球に迫る小惑星を爆破し、滅亡を防ぐために宇宙へ向かう主人公たち。彼らの使命は壮絶なものでしたが、特に印象的だったのは、遠隔装置が故障し、人力で起爆装置を押さなければならなくなったシーンです。最後の瞬間、ハリー(ブルース・ウィリス)は若き隊員を帰還させ、自ら小惑星に残り、命を懸けて人類を救いました。
このシーンは、「未来を託すことの勇気」を象徴しているように感じました。ハリーは、自分が犠牲になることで、若者たちが未来を生きられるようにと願ったのです。
教育もまた、次の世代へバトンを渡す営みです。親や先生は、子どもたちが自分の力で未来を切り開けるよう、全力で支えます。そして、時に厳しい決断をしながらも、彼らが自分の道を歩めるように後押ししていく——それはまさに、未来を託す勇気ではないでしょうか。
新年度が始まり、子どもたちにとっても新たな挑戦の季節です。彼らが自分の道を進めるよう、私たち大人がしっかりと支えていきましょう。
来月もよろしくお願いいたします。